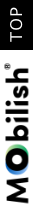MaaS関連サービス
2025.09.24
区民主体の新交通サービス導入を後押し 移動と生活をより快適に― オンデマンド交通「足タク」 他(東京都足立区)

東京都足立区

東京都北東部に位置する人口約70万人の区。日光道中最初の宿場町・千住を擁する歴史の街で、明治以降の工業化と鉄道網の発達に伴い発展を続けてきた。荒川・綾瀬川の水辺と、西新井大師やしょうぶ沼公園などの名所に恵まれる。区内はJR・私鉄・地下鉄など計8路線が通り、とりわけ5路線が乗り入れる北千住駅は1日当たりの利用者が非常に多い主要駅として知られる。
お話いただいた方
足立区都市建設部
交通対策担当
部長 長澤 友也 様
交通対策課 新たな交通担当
係長 長沼 佑貴 様
係長 長谷部 泰人 様
区内の新交通サービス第1号
――足立区で運行されているオンデマンド交通サービスについて教えてください

長谷部様
足立区で行っている新たな交通手段の1番目のサービスが足タクです。足立区北西部の入谷、鹿浜といった地域で運行しているデマンドタクシーで、昨年(2024年)令和6年6月から令和7年3月まで実証実験を行い、今年4月から本格運行に移行しました。
乗合型ではなく、実際のタクシーの運賃に対して差額を補助する形になっています。事前に利用者登録をすることで、自宅と地区内の乗降スポットや、乗降スポット間の移動に利用できます。料金は迎車料金と運賃の合計が2,000円未満の場合は500円、2,000円以上の場合は1,000円です。70歳以上の方や障がい者手帳をお持ちの方などは100円引きになります。
配車は電話予約のみで、月当たりの利用制限を8回に設定しています。
――足タクの実証運行スタートまでの経緯を教えてください。対象のエリアにはどのような課題がありましたか?

長澤 様
足タクの対象エリアである入谷・鹿浜地区は、区全体に対して行った交通に関する意識調査で、他地区に比べて交通不便度が高い結果が出た地域です。駅やバス停、スーパーや病院など多くの人にとって利用頻度の高い施設が広く点在している関係で、バスのような定期運行型のサービスでは利用ニーズに応えきれないと考えました。
また、もともと自家用車の所有率も高く、それほど公共交通を利用しない方も多かったり、高齢の方から駅やバス停までの移動に苦労している声も聞かれました。その結果、利用者が必要な時に自宅から利用できる、タクシーに近い交通手段が最もニーズに合致していると考えました。
そういった背景から既存の公共交通を補完する移動手段の検討が始まり、昨年6月からの実証実験に至っています。

利用実態を分析したところ、70代、80代以上の利用が大半で、概ね想定していた結果です。1日当たりの利用件数は10件ほどで推移しています。約70%の方が月に1、2回の利用で、月7回以上の利用は約3%。週初めの利用が多く、午前中の利用が7割を占めており、医療施設での乗り降りが多いなどの利用傾向が分かっています。
こういった利用実態を分析したうえで、①1日の平均利用件数、②協力タクシー事業者3社以上の継続、③周辺のバス路線への影響が軽微であること、④利用満足度が50%以上であること、この4つの指標を満たしていることから、本格運行への移行が決まりました。利用者へのアンケート調査から足タクに寄せられた改善点として「乗降スポットを増やしてほしい」「乗降スポット間の移動をできるようにしてほしい」などがありました。実証実験開始時に25カ所だった乗降スポットを令和7年9月現在では30カ所に増やしていますし、スポット間移動にも対応しました。
運用面においては、タクシー事業者の負担軽減にも取り組んでいます。運賃の差額を区が負担するという制度設計上、タクシー事業者側の精算事務作業が複雑化し負担となっていました。その省力化を目指して今年5月から足タクの利用実績管理システム(※)を試験的に運用しています。
※利用した情報ごとにシステム入力すると、月ごとに集計し区への提出書類が自動生成される。また、挙証資料である領収書をカメラ撮影すると自動保存され、また自動読み取り機能により運賃の差額もシステムが行う。
足タクに続く新交通サービスの検討もスタート
――足タク以外にも新しい交通サービスの実証実験が始まっています。

長谷部 様
足タクとは別に、地域内交通導入サポート制度を活用した実証実験が今年8月から常東地区で始まりました。この制度は、地域の交通課題を最も把握している住民が主体となって取り組む活動に対し、区が技術的なアドバイスや財政支援を行い、持続可能な移動手段を確保していく制度です。
常東地区は北千住駅東側に位置するエリアで、バス路線の運行が令和6年3月に終了したことで、代替の交通手段を求める意見が挙がっていました。そこで、地域住民から提案があった、幅広い世代が利用できる新交通サービスの導入の検討が始まり、乗合型のAIオンデマンド交通サービスの実証実験を行っています。区域内の指定のスポットで乗り降りできるサービスで、週2日運行しています。
埼玉県境に位置する花畑地区では、定時運行型の循環バスの実証実験を今年10月末にスタートさせます。花畑地区は、もともと交通の不便を解消するためのバス運行の社会実験を行っていましたが、本格実施に至らなかった経緯があります。より高齢の方でも利用しやすい交通手段を求める声が挙がっており、定時定路線型のサービスを試験運行します。
住民主体で考案する新交通サービスを後押し
――今後の取り組みについての考え方をお聞かせください。
長澤 様
足立区では地域内交通導入サポート制度を設けており、国の法律の枠組みの中で住民が主体となって地域内交通のあり方を検討し、行政側も支援していく仕組みを採っています。常東地区と花畑地区をモデルケースとして進めており、この取り組み状況を区内の他の地域に展開していく際の参考にしていきたいと考えています。
基本的には、現在のバス路線の維持をベースに地域交通の整備を考えていくべきだと思います。一方で、高齢化が進むと、今まで利用していたバス停まで行くのも難しくなってしまうケースが出てきます。高齢の方が今の生活スタイルを変えずに長く快適に過ごしていけるように行政が支援していくことも重要です。そういった部分を新しい交通サービスでカバーしていきたいと考えています。
もちろんコスト面を考慮する必要はありますが、できるだけ地域の意見に沿う形で交通サービスを整備していくことを目指しています。