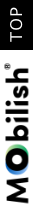お役立ち情報・資料
2025.06.30
ドコモ・バイクシェアの自転車型新モビリティ ペダルなしで進む快適な移動体験

今年で設立10年を迎えたシェアサイクルサービス「ドコモ・バイクシェア」。街中を走る赤い車体の自転車に見覚えのある方も多いと思います。累計利用回数が1億回を超えましたが、新しいモビリティの導入に向け、広島で実証実験を行っています。今回は、注目の新型モビリティを体験してきました。
ドコモ・バイクシェアのバイクシェアサービスとは?

ドコモ・バイクシェアが提供するシェアサイクルサービス。公式アプリを利用して、近くのサイクルポート情報を検索でき、手軽に自転車を借りられます。サイクルポートは駅周辺などアクセスしやすい場所にあり、乗りたい時に借りて、目的地周辺で返却できます。主要交通がカバーしていないエリアへの移動を実現する”ラストワンマイル”のサービスとして多くのユーザーに親しまれています。
新型モビリティは 自転車型の新しい乗り物

新型モビリティは電動キックボードなどと同じく特定小型原付に区分されますが、形状は従来機と同じ自転車タイプ。電動モビリティのリーディングカンパニーであるYADEA社の既存モデルをもとに開発したオリジナルの車両で、重量は28.6キロ、耐荷重は120キロ。最高速度は時速20キロです。安全面への配慮から、電動キックボードに見られる歩道走行時の「特例モード」(時速6キロ制限)は非搭載としています。

全体的なデザインは自転車と同じですが、ペダルがありません。足の置き場は固定されていて回転しません。電動キックボードのようにハンドルにあるアクセルで加速して進むのでペダルをこぐ必要がありません。

車体の解錠作業は従来機より手軽になりました。専用アプリのカメラ機能でシートポスト後方に設置されたQRコードを読み込んで解錠を進めるだけ。

ウインカーはハンドルの端に設置されています。ハンドルのモニターに左右のウインカーのボタンがあり、押すとライトが緑から黄色になり点滅します。再度ボタンを押せばライトが緑色に戻ります。

ウインカーボタンがあるモニター部分では、速度やバッテリー残量も表示されます。

タイヤは20インチで、特定小型原付に区分されるモビリティの中では大きなサイズ感。電動キックボードは車輪が小さく、ちょっとした段差でも衝撃を感じますが、この新型モビリティはタイヤが大きく、サスペンションも効くため段差でも安定感を発揮します。

かごに重い荷物を入れると、曲がる時にハンドルを取られてバランスを崩しやすく危険です。新型モビリティの荷物かごはハンドルを操作してもまっすぐなまま。転倒するリスクを考慮した安全設計です。

サドルの高さ調整も簡単。引き上げるとサドルが取れてしまう自転車もありますが、新型モビリティのサドルは取り外しができないタイプ。誤って外れてしまう恐れがありません。
新型モビリティで公道を走ってみました

ヘルメットをかぶってサドルにまたがり、まずは軽く練習です。操作するのはハンドルとアクセルのみ。足は置き場に載せたままで進むので、まさに自転車と電動キックボードの中間の乗り物といった印象です。
操作の説明を一通り受けて、いよいよ出発。ハンドルに設置されているアクセルを手前に回すと加速します。アクセルを勢いよく回しすぎると、急発進してしまうので注意が必要。初めてだと最初は少しスピード感に驚くかもしれませんが、最速でも20キロなのでしばらくすると慣れました。加速はとてもスムーズでペダルをこぐ必要がないので快適でした。

既存のモビリティとの比較
電動キックボードで車道を走る場合は、隣を車が通るたびに少し怖いですが、このモビリティは安心感がありました。立ったままになる電動キックボードと違って、座った状態で運転できるのでより安定感と安心感がありました。
車道で脇の段差を乗り越えるとき、車輪が小さい電動キックボードはそれなりの衝撃があります。足の置き場の幅も狭いことからバランスを崩さないか心配になることがありました。一方、自転車型であるこの新型モビリティは、電動キックボードと比べてタイヤサイズが大きく、段差を乗り越える際の衝撃もそれほど感じずに運転できます。
通常の自転車と比較しても、加速がスムーズでペダルをこがなくても進んでいくのは快適です。ちょっとした移動にはもちろんですが、少し長めの距離を移動する時にも便利だと思いました。
新型モビリティは広島で実証実験中
新型モビリティは現在、広島で実証実験中で、1分15円という料金設定で運用されています。ドコモ・バイクシェアのブランドカラーは赤色ですが、現在実証実験中の新型モビリティは白基調となっています。これは、新型も既存ポートで運用する際に、赤色の従来機との見分けをつきやすくするため。ただ、車体の色については現在検討中で、商用稼働する際には白から変更となる可能性もあるとのことでした。
ドコモ・バイクシェア新型モビリティについてお話しいただきました!

株式会社ドコモ・バイクシェア
モビリティUX部
部長 石橋 毅一 様(左)
モビリティUX部
モビリティUX担当課長 塩谷 圭一郎 様(右)
新型モビリティ導入へ
新型モビリティの車両は、複数の候補中から選定を進め、一般的に多くの人が乗り慣れている形状の「自転車タイプ」を採用しました。自転車と同じ操作感で扱える車両なので、幅広いユーザーの方々にご利用いただけると考えています。特定小型原付の中で一番タイヤサイズが大きく、安定感のあるモビリティを選んでいます。メーカーであるYADEA社もモビリティの生産と市場投入において信頼性が高く、ユーザー様にも安心してご利用いただけると考えています。
夏場の移動もより快適に
これまでは基本的に自転車をシェアリングさせていただいてきましたが、新型モビリティは従来の自転車とは異なる特定小型原付という新しい区分の乗り物です。シェアサイクルの利用回数の傾向を見ていると、もっとも利用が伸びる春先や秋口に比べ夏場は減少傾向になりますが、新型モビリティは夏場の移動により適していると考えています。
安全確保を最優先し信頼感を勝ち取る
安全面への配慮を重視しています。速度を6キロに制限して歩道を走行できる「特例モード」を備えたモビリティサービスもありますが、モード切り替えが難しかったり、ユーザー様が速度を落とさず歩道を走行してしまうケースも指摘されています。新しいモビリティサービスに対する安全面への懸念が世間的にあることは事実です。こういった背景から、新型モビリティにはあえて歩道走行モードを非搭載としました。サービスの提供とともに、安全な交通空間の確保を強く訴えたいと考えています。
実証実験での知見を活かしてサービスの質を向上させる
広島で実施している新型モビリティの実証実験で、このモビリティの安全性が受け入れられ、ユーザー様に安心してご利用いただけるかをしっかり見ていきたいと思います。特定小型原付に批判的な意見もあることは理解していますが、便利であることは間違いありません。しっかり安全対策をとったうえで、安心してご利用いただきたいと考えています。
実証実験は今年9月までの約半年間を予定しており、さまざまな施策を通じて、ユーザー様の声をしっかり拾っていきたいと考えています。その中で見えてきた課題を次のステップに活かして改善し、本格導入につなげていきたいと考えています。